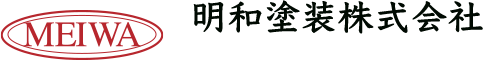塗装の不具合には色々な症状があり、なぜ起こってしまったのか原因が分かれば予防・対処も出来ると思いますので、ここで少し不具合の症状と原因、対策を書いていきます。
1、ブツ・ゴミかみ
塗装を仕上げていく過程で空気中のホコリや虫が付着したり、塗料や塗料を通すホース・スプレーガンに残っていた塗料カスが付着したりして、仕上げた時に塗膜に突起物が出来る事です。
対策
・塗装をする前にブースがしっかり機能しているか確認・清掃をする。水が使える環境なら壁や床を水で濡らしホコリが立ちにくくする。
・塗装対象物にエアブローやタッククロスを使用し付着しているホコリや研ぎ粉を除去する。塗装する本人についているホコリも払う。
・使用するスプレーガンやダイヤフラム等は使用後にしっかりシンナーを通し洗浄する。また塗料を通すホースなどは定期的にシンナーを循環させ塗料の付着を除去する、もしくは交換する。
・使用する塗料は、缶の中でダマになっていたりする事もあります。十分に撹拌をし、ストレーナーで濾して使う。
それでも塗装中に付着することは十分にあります。その場合、表面乾燥するのを待ち目の細かいペーパーで除去して再塗装を行ったりします。また塗装後であれば、ペーパーとコンパウンドを使い磨いて対応も出来ますが、付着物の芯が残ったりすることもあります。
2、タレ
インターバルをおかずに一気に厚塗りをしたり、シンナーの選定を誤ったりすることで塗料が重力に負けて流れてしまう事です。
対策
・重ね塗りをする際にインターバルをおいて塗膜が少し乾くのを待って塗り重ねる。
・気温・湿度を確認し、シンナーの番手・希釈量・塗料の粘度を調整する。
・スプレーガンのパターン・吐出量・エア圧をしっかり調整する。
塗装中にタレてしまった場合は、少し乾燥を待ち優しくペーパーて研磨し塗装溜まりを除去し、再塗装する。塗装後であれば、ペーパーとコンパウンドを使い磨いて対応できます。しかしタレた箇所の色が分離していたら磨いても色の違いが出る為、塗り直しが必要になります。
3、ハジキ
油分が原因で塗膜の表面張力が均一にならず、凹みが生じること。
対策
・塗装前に対象物をプレソルやシリコンオフをでしっかりと脱脂する。
・エアホースに油分が混じる可能性もあるので、エアホースをシンナーなどで洗浄する。
・使いさしのシンナーなどには不純物が混ざらないようにしっかり保管する。
上記を行ったうえでもはじく場合は、塗料に添加剤のハジキ防止剤を混ぜるのも一つの手段です。ただし分量を間違えると艶びきの問題や硬化不良を起こす可能性もあるので、必ず使用方法を確認の上で使用する事。
4、ガサツキ
塗料を希釈するシンナーの選定ミスによって乾燥が異様に早く対象物に塗料がなじむ前に粉状になって付着する為に発生したり、塗装の途中で補修を行った際のミストかぶり等によって発生します。
対策
・気温・湿度に合わせたシンナーを使う。塗る面積が大きければ、番手を少し遅い物に変えることで乾燥を遅らせ対象物にしっかりなじむようにする事が出来ます。
・塗って乾燥が始まっている箇所にミストがかかるとなじまずにガサガサになります。ガサガサになっているところにシンナーをかけることでなじむ場合もあります。
塗装後にガサついている場合は、ペーパーとコンパウンドを使用し磨くことで除去できることもあります。それでもダメな場合はペーパーでガサつきを除去し再塗装する必要があります。
※もちろん下地がガサガサした状態の上に塗装をした場合は間違いなくガサつきます。
5、艶びき
素材の表面が荒れていたり、下塗りの塗料の乾燥不足や研ぎの甘さによって、その上に塗装した塗料の樹脂が吸収され顔料だけが残り本来の光沢が出ていない状態のことをいいます。また膜厚が薄すぎても艶びきは発生します。
対策
・素材であれ下塗りであれ、しっかりと研磨する。番手の粗いものだけだと荒れた状態が取れないので細かい番手のペーパーでしっかり下地を作る。
・下塗りをしたいる場合は、しっかりと乾燥させ下塗りになじまないようにする。
・しっかりと塗料の基準膜厚を達成し、薄膜にならないようにする。
6、塗装ムラ
ムラには種類があり透けムラ・塗りムラ・メタリックのムラ等があります。見た目に色の濃淡があったり、下地の色が見えていたり、ムラは美観を損ねます。
対策
・透けムラの場合は、上塗りの塗装でしっかり色を隠蔽できて事が原因なので、インターバルをおいて塗り重ねしっかりと膜厚をつけ下塗りを見えなくする。また下塗りの色の選定間違いをするといくら上塗りを重ねても透けが発生しムラが取れないので注意が必要です。
・塗りムラは、塗り重なる場所やスプレーガンの動かし方が安定していないと、塗りすぎの部分や塗れていない部分などが出てムラになるので、スプレーガンの吐出量やエア圧、手の動かし方などを練習・確認する必要があります。
・メタリックムラはアルミ粒子が寝たり立ったり均一に並んでなかったりする事で色が黒っぽく見えたり白っぽく見えたりと斑になることです。これを防ぐには、インターバルを置きながら繰り返し塗り、クリヤーもカラーが少し乾燥してから塗る事で防げたり、均一に塗れるようにスプレーガンを調整したり手の動きを調整する必要があります。
7、白ボケ
ブラッシングともいい、対象物が冷えていたり、湿度の高い時に乾燥の早いシンナーで塗装したりすると、急激に溶剤が揮発し、その気化熱で塗膜の温度が下がり、湿度の高い空気の水分が塗膜に吸着することで白ぼけてしまう現象です。
対策
・気温が極端に低い日や湿度の高い日を避ける。避けることが出来ない場合は、ジェットヒーターなどで部屋を暖めてから塗装する。またシンナーを揮発の遅いものを選んだり、リターダー(白化防止剤)を使用する。
8、リフティング・ちぢみ
リフティングとは塗料を重ね塗りする際に、上塗り塗料の溶剤によって下地の塗膜や旧塗膜が侵され、シワシワにちぢれ塗膜が浮いてしまう現象です。特に弱溶剤系のフタル酸塗料で塗られている上に塗る場合は注意が必要です。誤って溶剤の強い塗料で塗ると高確率でリフティングが発生します。他にも下塗りの乾燥が不十分な状態で上塗りをすると、溶剤が乾燥していない塗膜に溶け込みリフティングすることがあります。
対策
・溶解力の弱い弱溶剤塗料を上塗りに使い、一度に厚塗りをしないようにする。また弱溶剤塗料で塗装を失敗し再度塗る必要が出来た場合は、しっかり乾燥させた上でちぢみ止めシーラーを使うのも手です。また2液のウレタン塗料などでウェットウェットで塗る場合、乾燥速度の遅い塗料の上に乾燥速度の速い塗料は使わず、乾燥速度の同じ塗料か上塗りの方が遅い塗料を使うようにする。ちぢみは一度発生してしまうと塗膜を剥離してしまう以外対処方法がありませんので、十分に注意が必要です。
9、ペーパー目
ペーパー目は、下地処理の際に使用したサンドペーパー(研磨紙)の傷や痕跡が、塗装後に表面に現れてしまう現象を指します。サンドペーパーの目が粗かったり、シンナーでの希釈が多い塗料で一気に塗りこんでしまったり、完成塗膜が薄かったりする事で起こります。これは仕上がりの品質を低下させ、美観を損なう原因となります。
対策
・粗いサンドペーパーで下地処理を済ますと傷が深く塗料で隠しきれないので、細かい番手で研ぎ直し傷を小さくしてから、しっかりと各塗料の指定膜厚値まで塗ることで見えなくする事が出来ます。またシンナーによる希釈が多すぎる塗料で一気に塗り込むと隠蔽性が落ちたり、塗膜の収縮が大きく完成塗膜が薄くなったりすることでペーパー目が見える原因となるので、シンナーの量を少なくするかインターバルを置きながら複数回に分けて塗り込むようにすることで解消する事が出来ます。
10、ピンホール
ピンホールとは、塗装面に形成される非常に小さな穴や気泡が乾燥後に表面に現れる現象を指します。原因には色々ありますが、一気に厚塗りをしたりインターバルをおかず重ね塗りをすることで、塗膜内に含まれる溶剤や空気が、塗料の乾燥過程で外に逃げることが難しくなり、その結果として小さな穴(ピンホール)が形成されるためです。また、パテを付けた際の素穴を見落としその上から塗装した際にその素穴がそのまま現れてしまうといった場合もあります。
対策
・硬い塗料で塗らず適量のシンナーで希釈し、一度に膜厚をつけすぎないように、またインターバルを置いて重ね塗りをしていく事で解消できます。またパテの素穴は研いだ跡エアで飛ばし確認し、素穴があればパテでしっかりと埋め上塗りをする事で解消されます。
11、パテ跡
パテ跡とは、塗りあがった塗装面にパテを塗った部分だけがくっきり浮いて見えてしまう現象です。原因には、パテを付けた後十分に研磨が出来ておらず周囲との段差が残ってしまっていたり、パテがしっかり乾いておらず塗装後に収縮しパテの際が浮いて出たり、パテと周囲の素材(例えば、金属やプラスチック)で塗料の吸い込み具合が異なる場合、乾燥後に塗膜の色や光沢が変わることがあります。
対策
・パテ跡が出ないようにするには、付けたパテをしっかり乾かし(時間が無い場合は近赤外線などを使用する)、ペーパーでしっかり段差が無くなるまで研ぐ(当て板等を使用する)ことで解消することが出来ます。また、素材による塗料の吸い込み具合の違いを無くすために、サフェーサーを塗ることで下地の違いを無くし均一な色や光沢を出すことで解消も出来ます。
12、塗装割れ(クラッキング)
塗装割れとは、温度、光・水・溶剤等によりもろくなり塗膜が割れたり、塗膜を厚くしすぎて表面と内側の乾燥速度にズレが生じて、乾く過程で先に乾いた表面の塗膜を割ってしまい、塗装面に細かい亀裂や割れが生じる現象を指します。この症状は、見た目にも不快であり、塗装の耐久性や保護機能に悪影響を及ぼします。
対策
・膜厚をメーカー指定の膜厚に抑えて塗る事で解消できます。また以前に塗られていて紫外線などで脆くなり割れている状態をリフレッシュする場合などは、割れた亀裂は塗装で埋まらないので一旦旧塗膜を剥がしてから塗装しないといけません。それ以外にも、硬化剤を要する塗料の場合は、配合率を間違えると一旦乾くものの後から亀裂が生じることがあるので、配合率を間違えないようにしましょう。